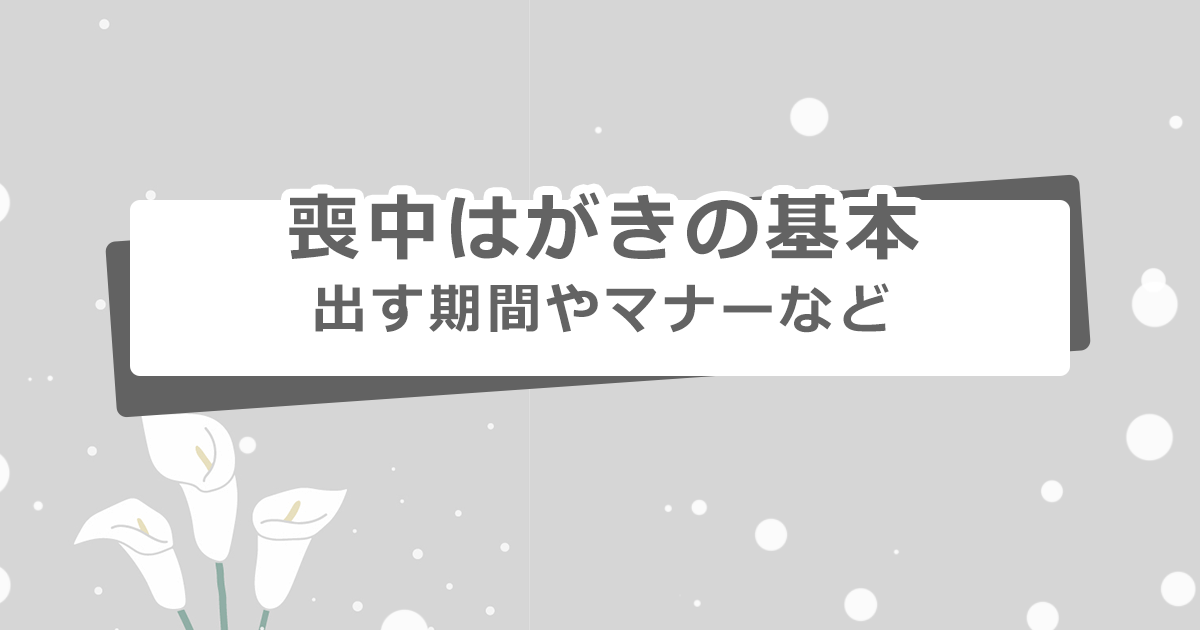実は、喪中はがきについてのマナーや出し方などの基本的な内容は、あまり知られていないと言われています。人生でそう多くない出来事なので詳しくなくて当然ですが、葬儀社などでは喪中はがきの相談も多いなど、実際に誰か近しい人が亡くなってから慌てる人が多いようです。
そこで今回は、あまり知られていない喪中はがきについて、出す時期やマナーなどもあわせてご紹介します。
喪中はがきの基本・マナー

一般的に私たちが喪中はがきと呼んでいるものは、『年賀欠礼(状)』『喪中欠礼(状)』といいます。喪中はがきは、喪に服している期間であることをあらかじめ年賀状のやりとりをしている人に向けて送るものです。喪に服する期間は一年とするのが一般的 で、多くの場合は一回忌の法要が終わるまでとします。
喪中は、おめでたい行事や式典、パーティーなどへの参加、大々的な遊びなどは控えるという習わしがあります。年々、この習わしへの意識は徐々に薄れてきていると言われていますが、「新年を祝うおめでたい年賀状は避けるべき」とされています。
喪中はどこまでの親族が対象なのか
喪中はがきに切り替えなければならないのは、どの範囲までの家族や親族が亡くなった時までなのでしょうか。一般的に、喪中はがきは二親等以内の親族が亡くなったときが対象 です。
二親等といっても、生計を別にしている祖父母や孫、兄弟姉妹の場合は対象にならないと解釈されるのが基本ですが、近年では生計を別にしている(別居している)家族であっても喪中はがきを出すケースが多いです。もちろん、父母、配偶者、子は生計を別にしていても一親等なので喪中はがきを出すこととなります。
喪中はがきは誰に出すのか
喪中はがきは、喪に服している期間のため新年のあいさつを控えるという旨をあらかじめ知らせるためのものです。そのため、毎年年賀状をやりとりしている人や、新年のあいさつをしている人に送ります。
ただ、プライベート上の付き合いがない、ビジネス上のお付き合いをしている人へは、知らせることがかえって余計な気遣いをさせてしまうからと、いつも通り年賀状を出すケースもあります。基本的に葬儀に参列して下さった人や、香典を頂いた方には出すと良いでしょう。
年賀はがきを送りあっている親族については、喪中はがきは省略するのが一般的 です。そして、年賀状を送る相手も喪中であることが既にわかっている場合、こちらからは出さなくても良いのではと思われがちですが、こちらからもきちんと出すのが基本です。
また、亡くなった当人の交友関係にも注意しなければなりません。亡くなった当人が年賀状のやりとりをしていた人たちにも、連絡漏れを防ぐために出来るだけ喪中はがきを出すようにしましょう。
喪中はがきを出す時期は?
喪中はがきを出すタイミングについて見てみましょう。喪中はがきは、だいたい11月から12月の初めまでに出します。あまり遅くなりすぎると、相手が年賀状の準備を始めてしまうからです。
もし、年末に不幸があった場合は、喪中はがきが間に合いません。こうした場合、喪中はがきは出さず、年賀状も出さないようにしておいて、松が明ける一月八日から節分までの期間に寒中見舞いを送ります。この寒中見舞いで、年始のあいさつができなかったお詫びと年賀状をくださったお礼などを伝えます。
一般的な喪の期間
一般的な喪の期間は以下の通りです。
- 両親(父母)・夫・妻・同居の義父義母:1年
- 祖父母:6ケ月(3ケ月~)
- 兄弟姉妹、子、同居の曾祖父母、別居の義父義母:3ケ月(~6ケ月)
- 義兄弟姉妹、孫:1ケ月(~3ケ月)
- 叔父叔母、伯父伯母、別居の曾祖父母:喪に服す期間としない
喪中はがきにおすすめのはがきと切手
通常はがきでは、料額印面が胡蝶蘭柄のものが喪中はがき用として定番化しています。図柄が印刷済の市販はがきに切手を貼って投函する場合は、「弔事用63円普通切手花文様」を使用することが望ましいでしょう。
喪中はがきの書き方・文例

まず、喪中はがきの一般的な構成について見てみましょう。
- 喪中につき年始のあいさつを控える旨を伝えることば
- 誰がいつ亡くなったのか
- 日頃の感謝のことば
- 日付、差出人
年賀状の場合は「謹賀新年」や「謹んで新年のご挨拶を申し上げます」あるいは「明けましておめでとうございます」などの賀詞ではじまりますね。喪中はがきの場合は、「喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます」とし、喪中により年始のあいさつができない旨を伝えます。
そして、次のように文章をすすめていきます。
- ○月に△△が天寿を全ういたしました
ここに本年中に賜りましたご厚情を感謝いたしますとともに明年も変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます
- 今年○○が△△月に永眠いたしました つきましては服喪中でございますのでお年賀の礼を差し控えさせて頂きます
本年中に賜りましたご厚情を感謝いたしますとともに
明年も変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます
皆様にはよき新年をお迎えくださいますようお祈り申し上げます
また、喪中はがきは、とても儀礼的な改まったご挨拶状ですので、伝統的な縦書きにするのが無難です。しかし、横書きで書いても問題はありません。
喪中はがきを受け取ったら

喪中はがきを受け取った時は、どのようにお返事したら良いのか悩みますよね。喪中はおめでたい行事を避けなければならないため、年賀状やおめでたい言葉は避けるのが一般的です。
こうした場合、寒中見舞いを送ると良いです。寒中見舞いは、松の明ける一月八日から節分までの時期で、寒さが厳しい時期の体調をねぎらう季節のあいさつ状で、何らかの事情で年賀状が送れなかった時によく用いられる手段です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 喪中はがきは必ず出さなければいけないのですか?
A. 法律で定められているものではありませんので必須ではありません。ただし、年賀状のやりとりをしている方への礼儀として出すのが一般的です。
Q2. 喪中はがきはいつまでに出すのがマナーですか?
A. 相手が年賀状を準備する前に届くように、11月〜12月初旬までに投函するのが望ましいです。
Q3. 年末に不幸があった場合はどうすればいいですか?
A. 喪中はがきが間に合わないため、年賀状は出さずに、1月8日〜節分の間に「寒中見舞い」を送りましょう。
Q4. 喪中はがきはどの範囲の親族が亡くなったときに出すのですか?
A. 基本的には二親等以内(父母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・孫)が対象です。ただし、近年は別居していても出すケースも増えています。
Q5. 喪中はがきを受け取ったらどう対応すれば良いですか?
A. 年賀状やお祝いの言葉は避け、代わりに「寒中見舞い」を送ってお悔やみと気遣いを伝えるのが一般的です。
喪中はがきの基本 まとめ
今回は、喪中はがきの基本やマナー、文例についてご紹介しました。タイミングによっては喪中はがきを出すことが困難なケースもありますが、そうでない限りは年賀状のやりとりをしている人への礼儀として出しておきたいものです。
あまり知られていない喪中はがきの基本は、今回の内容でカバーできるのではないでしょうか。困ったときには、ぜひ参考にしてみてくださいね。